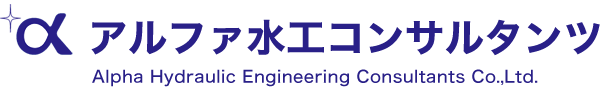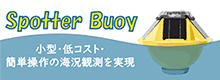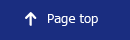水環境 - 貴重なはまべ
みずべを保全する

日本最大の砂嘴の内湾は
貴重な生物の棲む干潟・藻場
(北海道野付崎)
島国である日本は、近海では暖流と寒流が流れ、豊かな生態系が育まれています。海岸、河口干潟等の沿岸域は、多様な生物の生息場であり、これらは水質浄化機能や生物生産だけでなく、景観やレクリエーション等の社会的機能をも有しており、私たちに豊かな恵みを与えてくれます。このほか海藻・海草の藻場では、光合成による二酸化炭素の吸収量のうち海中・海底等で長期に渡って固定され、大気から隔離される効果が、近年、地球温暖化緩和策となるブルーカーボンとして着目されています。
従来、海岸の砂浜やサンゴ礁には波浪を低減する効果があり、私たちの国土や背後にある建物や道路等の資産と周辺の環境を護る天然の防波堤となってきました。しかし、近年、地球温暖化の進行に伴う自然災害の頻発・激甚化もあって、日本沿岸各地で海岸侵食や干潟の消失の問題が深刻化しており、豊かな海岸や干潟を未来に引き継ぐための対策の実施が喫緊の課題となっています。

繁殖のため干潟に飛来した
タンチョウ(北海道野付崎)
流砂の堆積で穏やかな場所に形成された干潟を保全するためには、波浪や潮汐による底泥の移動メカニズムや底泥中の環境変化を把握し、底泥を安定させ生物の生育環境を良好に保つ必要があります。流域に築造した構造物などの影響により侵食傾向となることが多く、底泥の移動を制御することが課題となります。当社は、
河川流量調査・河道の地形測量・調査等を立案・実施します。

海岸侵食により基礎が
むき出しになっている倉庫
さらに、流況と流砂を考慮する
河床変動解析や海浜地形変化解析等の数値シミュレーション等を行い、現況と対策案を比較した上で、河岸侵食や波浪・潮流を抑制する最適な対策工について検討・提案します。
海岸侵食に対しては、対象海岸における広域的な土砂の移動メカニズム等を解明し、長期的視点で持続可能な海岸の保全を図っていく必要があります。

海岸侵食により崩落した道路
当社は、近年の海岸侵食・浸水被害の発生状況を踏まえた上で、
植生調査・汀線測量・水質調査・底質調査・流況調査等を立案・実施し、
汀線変化解析などの数値シミュレーションを行い現況と対策案を比較した上で、突堤・消波堤・養浜など、最適な海岸保全施設の整備計画について検討・提案します。

海底に沈んだガレキと赤潮
(植物プランクトンの大量発生)
日ごろ目にすることのない水の中にも、多種多様な生物による生態系がなりたっています。私たちが生きるために口にするあらゆる魚介類もその食物連鎖の典型的な産物です。この生態系システムのバランスが崩れると、取り返しの付かない変化が生じます。有害物質は食物連鎖によって残留・蓄積されます。人間が作り出した有害物質もあります。環境の変化によって絶滅の危機に瀕している水棲生物もあります。人類が環境と共存するために、科学技術による水環境の保全、創出に取り組んでいます。
<関連技術サービス>